配偶者居住権と敷地利用権

配偶者居住権や敷地利用権の制度は、自宅不動産(建物・敷地)の価値を、「配偶者が住む権利」と「他の相続人が所有する権利」に分けて相続するしくみです
配偶者居住権の設定により、建物の価値を配偶者が住む「配偶者居住権」と他の相続人が所有する「負担付所有権」に分けることで、配偶者には現金預金等を多く相続する余地ができます。
敷地利用権とは、建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む)を、配偶者居住権に基づき使用する権利のことをいいます。
負担付所有権の「負担付」とは、配偶者居住権という「(所有者の立場からは)義務を負った」所有権という意味です。
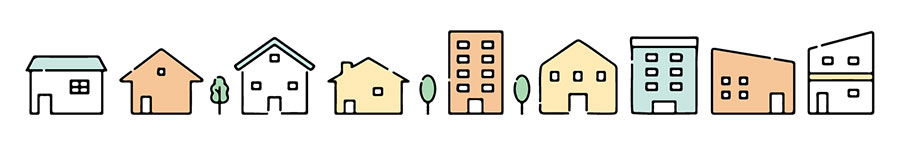
配偶者居住権が成立するには
- 遺された配偶者が、被相続人(亡くなった人)の法律上の配偶者であること
- 配偶者が、被相続人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
- ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判、のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
この3つを満たす必要があります。また、第三者に対抗するには登記が必要です。
次に、対象となる建物は被相続人の単独の名義または被相続人と配偶者との共有名義に限られます。配偶者以外の人との共有の建物には認められません。
敷地に関しては、配偶者以外の人との共有であっても認められます。

配偶者居住権で居住する場合の決まりごと
配偶者と所有者との法律関係
- 建物の所有者に無断で賃貸するなど、これまでと違う用法で建物を使用してはいけない
- 建物の修繕に関する費用は、配偶者が負担する
- 建物の所有者に無断で増改築はできない
- 建物に関する通常の必要経費は、配偶者が負担する
- 固定資産税は、建物の所有者が納税義務者なので所有者が負担するが、所有者はその分を配偶者に請求できる

配偶者居住権を設定する方法
1.死因贈与契約書を公正証書で作成し、仮登記を行う
配偶者と、他の相続人が不仲であった場合など、配偶者居住権を確実に得るために仮登記を行うことができます。
被相続人の死後、本登記をします。
配偶者居住権を設定するための、最も手堅い方法です。

2.遺言書に書き記しておく
遺言書に、配偶者居住権を設定するように記入しておきます。
遺言書の作成方法としては、公正証書遺言、その次に法務局の自筆証書遺言保管制度だと確実性が高まります。
遺言書を登記原因証明情報として、配偶者居住権を登記します。
しかし他の相続人が反対している場合、(登記実務の手順上)配偶者居住権が登記できなくなることもあり得ます。

3.被相続人の死後、遺産分割協議書を作成する
一般的に遺言書があってもなくても、遺産分割の内容について相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成できます。
配偶者居住権を設定する内容の遺言書がなくても、全員の合意があればこの内容についての遺産分割協議書を作成できます。
遺産分割協議書を登記原因証明情報として、配偶者居住権を登記します。
言い換えれば、登記原因証明情報となる遺言書もなく、さらに他の相続人の反対に合えば、配偶者居住権は登記できません。

この制度を利用するメリット
配偶者の老後の生活に対する配慮
配偶者が、自宅建物に住み続けたいためにその所有権を相続すると、現金預金を多く相続できないため生活資金が不足することがあります。
配偶者居住権の設定は、所有権がなくとも安心して建物に住むことができ、生活資金も確保できる方法です。
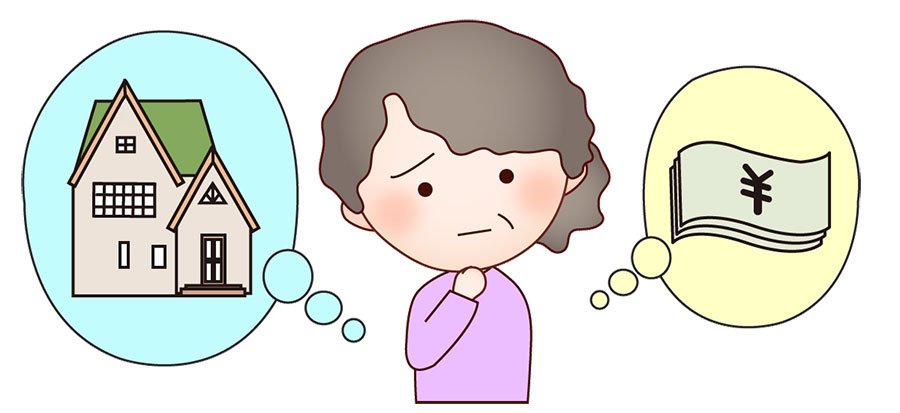
二次相続での節税効果
配偶者居住権は配偶者の死亡や存続期間満了により消滅すると課税関係なしとなります。このように消滅して課税関係なしになった場合は、二次相続(配偶者の死亡による相続)で相続税の節税効果が期待できます。

後継ぎ遺贈が可能になる
被相続人と配偶者との間に子がいない場合、建物を配偶者の所有にすると配偶者が死亡したときに配偶者の家系に当該建物が相続されます。
これを避けたい場合は、配偶者居住権で配偶者には居住する権利だけを保障し、所有権を自分の血縁者である他の相続人にしておけば、配偶者の死後は被相続人の家系に相続させられます。
上記の例は、今回の自分の死亡により開始した相続の、次に起こる相続についての指定ですが、これは後継ぎ遺贈といい、基本的に遺言書ではできない手続きです。
なお後継ぎ遺贈と同様の効果を得る方法としては、「受益者連続信託(信託法第91条)」を活用する方法があります。

考えられるデメリット
配偶者居住権がついたままでは、空き家になっても実質的には売却できない
自宅建物の所有者は、施設に入るなどの理由で配偶者が退去し空き家となった建物の売却を考えることもあると思います。
この場合は、配偶者が残っている配偶者居住権の価値を放棄する、または配偶者と所有者との合意解除によって他の相続人(この場合建物の所有者が考えられる)に当該価値を贈与・譲渡して、建物に関する負担付所有権を完全所有権にしてからでなければ売却できません。

配偶者居住権の贈与・譲渡は課税の対象となる
配偶者居住権は配偶者の死亡またはあらかじめ定められた期限をもって消滅し価値はなくなります。
この時を待たずして当該権利を他の相続人に贈与・譲渡するときは、配偶者居住権の価値は課税の対象(贈与税・譲渡税)になります。

配偶者居住権は第三者に譲渡できない・相続もない
贈与・譲渡できるのは相続人のみです。また、配偶者が死亡すると配偶者所有権は消滅するので相続財産にはなりません。



