配偶者居住権を含んだ遺産分割の例

配偶者居住権と敷地利用権の価額
相続税申告における配偶者居住権評価額を用いる方法
配偶者居住権と敷地利用権は、一定の計算式により価値が算定されます。
配偶者の年齢が若いほど、それら権利の価値は上がります。
建物の価額と配偶者居住権の価額の関係
居住用建物の価額=居住用建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額

敷地の価額と敷地利用権の価額の関係
敷地の価額=敷地の相続税評価額-敷地利用権の価額
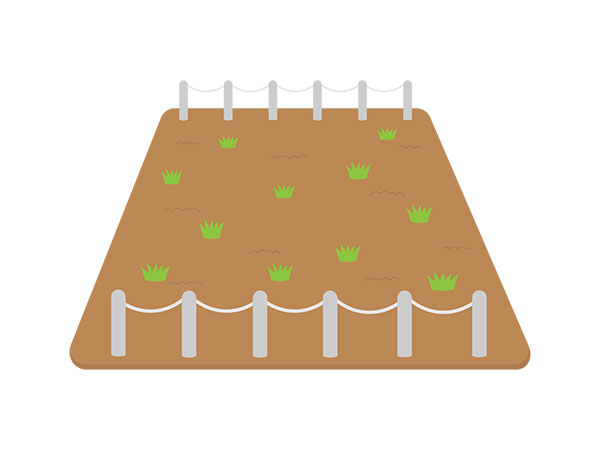
負担付所有権とは
価値が減額された居住用建物等に対する居住権のことを、負担付所有権といいます。配偶者を終身またはあらかじめ定めた期間が終了するまで住まわせる、という負担が付いた所有権という意味です。

遺産分割の例として、数字をあてはめてみる
配偶者居住権なし
夫が亡くなり、妻と長男が相続人で、相続財産として自宅建物が3,000万円、現金預金が2,000万円だったとします。この例では法定相続が妻・長男とも1/2ずつです。
妻が建物に住み続けたいと希望し妻単独の名義にするため、建物3,000万円を妻のものとすると、長男の相続分が現金預金2,000万円となり法定相続より500万円不足してしまいます。
こういった遺産分割が相続人の間で合意できればいいのですが、そうでなければ妻は現金預金を相続できない上に、長男に代償金を500万円払わなければなりません。

配偶者居住権あり
先の例で、仮に配偶者居住権が1,000万円と計算されたとします。そうすると建物の所有権の価値は2,000万円です。
妻の相続分は、建物の配偶者居住権1,000万円(所有権としての持分は0)に現金預金1,500万円を加えると2,500万円となり、代償金500万円を払うどころか1,500万円の現金預金を相続できることになります。
一方長男は、自宅2,000万円(所有権としての持分は10割)と現金預金500万円の合計2,500万円を相続できます。



