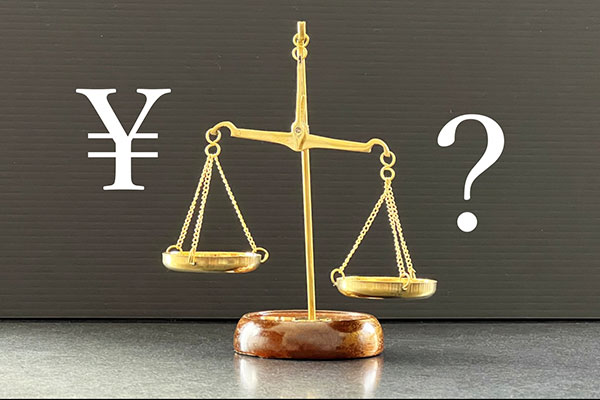本人に財産があまりない場合には成年後見人等をつけるほうが、楽になることがある
2023年7月27日
介護のプロであるヘルパーに介護を頼むように、専門職後見人等に財産管理を依頼する 財産管理や身上監護を専門職に任せることにより事務的負担や精神的負担を軽く 親族後見人等や実質的に成年後見人等の業務をされている親族が、高齢で […]
成年後見制度を神戸市の助成や法テラスの法律扶助でもっと使いやすく
2023年7月26日
報酬支払いに対する助成は、神戸市成年後見制度利用支援事業 本人の財産が一定の基準より少なく、成年後見人等が神戸市に住民票があるときに報酬の助成が受けられる 成年後見人等は、親族か専門職かにかかわらず、家庭裁判所へ成年後見 […]
後見制度支援信託とは
2023年4月10日
専門職後見人は親族後見人へ引継ぎ後辞任するので、報酬支払いは1度限り 後見制度支援信託を利用する例として、家庭裁判所へ成年後見開始の申立てをし、親族後見人が選任されるとき、後見制度支援信託の利用の意思の有無を確認されるこ […]
法定後見制度を利用するには
2023年4月3日
後見等開始の審判の申立て 申立てができる人 本人の判断能力の低下が見られた場合、本人、4親等内の親族または市区町村長などが申立人となって、家庭裁判所へ後見(保佐・補助)開始の審判(後見人等の選任)の申立てをすることができ […]
成年後見人等のルール
2023年2月23日
成年後見制度を利用すれば、判断能力が低下した人を守れるというメリットがあるのですが、これまで法律行為を自分で行ってきた人が被後見人等になってしまうと、家族や関係者にはこのしくみのデメリットが見えてくることがあります。 事 […]
法定後見制度と任意後見制度
2023年2月23日
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。 法定後見制度とは 「法定後見制度」とは、本人の判断能力の低下が見られたときに家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等を選任するものです。 法定後見制度には3 […]